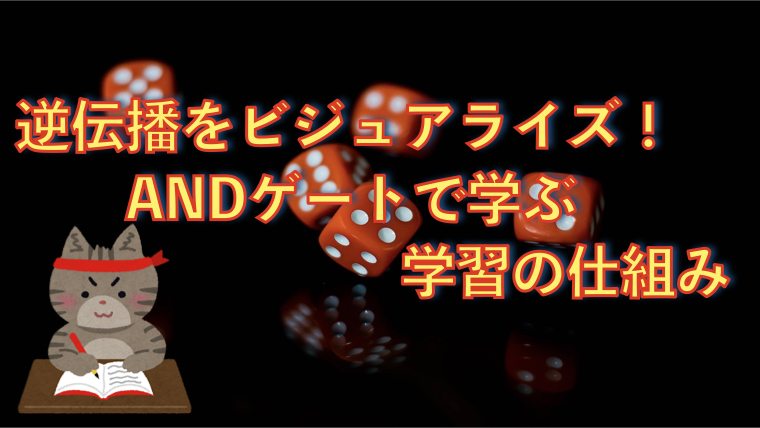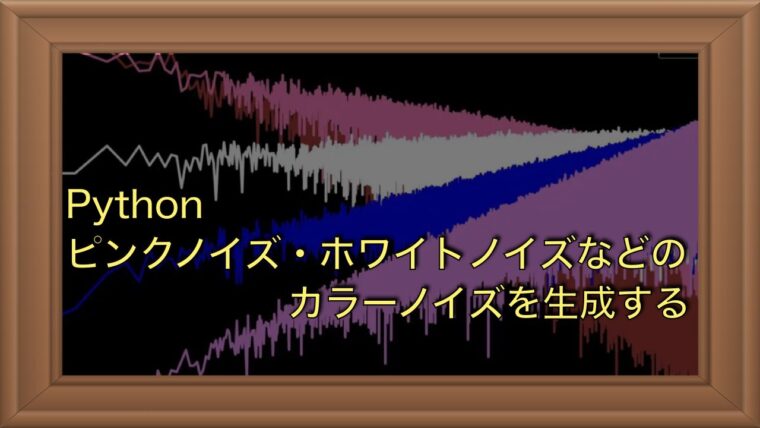大規模言語モデル(LLM)は本当に”理解”しているのか? 個人的な視点からの考察
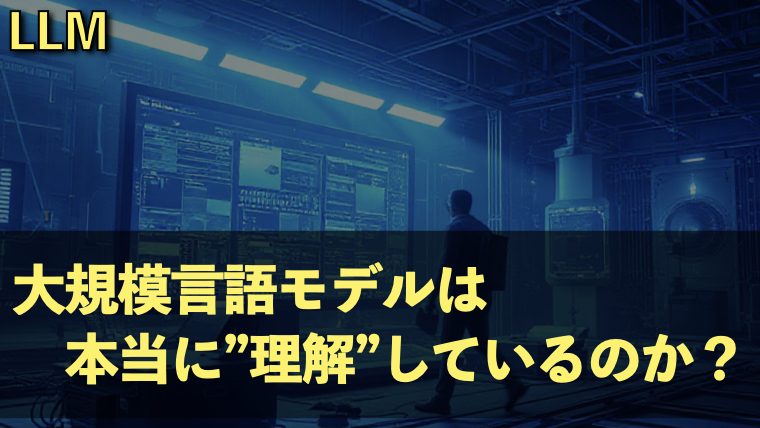
近年、大規模言語モデル(LLM)が急速に進化し、私たちの日常や仕事にもその影響が及んできています。自然な言語で対話し、高度な問いにも応答できるその姿から、まるで「理解している」かのように見えることもあります。私はLLMの研究者ではありませんが、画像認識の現場からディープラーニングに携わってきた一人として、この「LLMは本当に“理解”しているのか?」という問いが気になっていました。
この記事では、あくまで個人の立場から、LLMの“理解”とは何か、人間の理解とどう異なるのかについて、整理しながら考察してみたいと思います。

いつもは、プログラミングをメインに記事を書いていますが、今回はエッセイ的な記事を書いてみました。
というのも、最近LLMの「理解」に違和感を覚えているからです。
「私と違う!」という人もいるかと思いますが、あくまで個人の意見ですのでその辺りを理解していただけると幸いです。
LLMの『理解』という表現に感じる違和感
Transformerの発表以降、ものすごい速度での大規模言語モデル(LLM)の進化がとまりません。ChatGPTに代表されるLLMは、自然な言葉で対話でき、複雑な問いに答え、時には人を凌駕する能力を発揮します。
LLMの記事などでは、度々「理解」という言葉が使われますが、調べてみると、ここで使われている「理解」は、人間の「理解」とは異なるもののようです。
ここで、「AIの理解とは」となに?という疑問が湧きます。
まずは、これを少し掘り下げてみました。
人間とLLMの『理解』の違い──“浅い理解”とは何か?
私たちはLLMの流暢な応答に接すると、まるでそこに人間のような知性や「理解」があるかのように錯覚しがちです。しかし、その根底にあるのは、あくまで「次に続く単語の予測」という、一見すると極めて単純なメカニズムに過ぎません。
この「予測」は、膨大なテキストデータから学習した単語間の統計的な関連性に基づいています。まるで、過去に聞いたパターンを記憶し、次にどんなパターンが来るかを推測するようなものです。
この意味で、LLMの「理解」は、人間が持つような意識や感情、常識、そして現実世界との物理的なインタラクションに裏打ちされた深い洞察とは一線を画します。
それは、むしろ「巨大な連想記憶」と表現するのがふさわしいと考えています。
特定の単語やフレーズが与えられると、LLMはその記憶の広大なネットワークの中から、統計的に最も関連性の高い別の単語や概念を瞬時に「連想」し、続く単語の候補を絞り込みます。この連想の連鎖により、LLMは自然な会話を可能にしています。
個人的には、LLMの理解は、人間の理解を「深い理解」と定義すると、統計的連想によるパターン認識による「浅い理解」であると考えています。
文脈という“フレーム”がもたらす知的な絞り込み
しかし、「単なる予測器」がなぜこれほど高度なタスクをこなせるのでしょうか。その秘密は、LLMが獲得した「文脈(コンテキスト)処理能力」にあるのではと考えます。
これは、私たち人間が会話を始める際に「これは以前、〇〇さんが話していた件ですが…」と前置きをして、聞き手との間で話の「フレーム」、すなわち議論の範囲や前提を共有しようとする行為に似ています。
LLMもまた、プロンプトとして与えられた大量の資料やこれまでの会話履歴を、その時点における「フレーム」として認識します。
このフレームは、人工知能が長年直面してきた「フレーム問題」――関連性のない膨大な情報をいかに無視し、関連情報に焦点を当てるかという課題――に対し、明示的なルールではなく、統計的な学習を通じて動的に解決策を提供するものです。
LLMでは膨大な学習データとユーザーとの対話により「フレーム」が確立されることで、LLMは自身の「巨大な連想記憶」の中から、与えられた文脈という「条件」に基づいて、次に予測すべき単語の確率分布を「ベイズ的に狭める」ことができます。
つまり、コンテキスト(人間とのやり取りや資料など)が加わることで、無数の単語の選択肢が、その文脈において最も適切・かつ自然な言葉へと絞り込むことが可能になります。
このように考えると、「単なる次の単語の予測」で、うまく会話をおこなうことができる理由に納得がいきます。
スケールこそが“知性”を生んだ──LLMの性能飛躍の理由
今日のLLMが驚くべき能力を発揮できるようになったのは、この「巨大な連想記憶」と「文脈による予測の絞り込み」を可能にする「巨大なスケール」が実現したからに他ならないと私は考えています。。
まず、インターネット全体に匹敵する「膨大な学習データ」。これにより、LLMは言語の複雑なパターンと世界の知識を、人間では到底習得しえない規模で吸収しました。
次に、その知識を記憶し、複雑な関連性をエンコードするための「巨大なモデルサイズ」。数兆のパラメータを持つモデルは、このデジタルな知識の海を整理し、必要な時に引き出す「脳」の役割を果たします。
そして、LLMが急速に性能向上した理由として私が考えるのが、「膨大なコンテキストウィンドウ」です。初期のモデルでは1024トークンや4096トークンと非常に小さかった一度に処理できる情報の範囲が、数十万、さらには100万トークンを超えるまで拡張されたことで、LLMは文書全体、あるいは複数の情報源にまたがるような長期的な文脈を深く理解し、より詳細な「絞り込み」が可能になりました。
この三つの「巨大さ」が相乗効果を生み出すことで、LLMは単なる予測器から、要約、翻訳、推論、そして創造的な執筆といった、これまで人間が得意としてきた多くのタスクにおいて、目覚ましいパフォーマンスをだせるようになったのではないでしょうか?
LLMの“理解”は人間とどう違うのか──私の結論
LLMの“理解”は、人間のそれとは本質的に異なるプロセスに基づいています。人間が「次の単語を逐次予測して会話しているわけではない」という事実からもこれは明らかでしょう。
LLMは、膨大な学習データ、巨大なモデル構造、そして広大なコンテキスト処理能力によって、文脈から「意味らしきもの」を推定する力を獲得しています。
しかし、私たちが日常的に用いる「理解」とは異質なものです。人間の“理解”が、経験・抽象・感情・意図といった多層的な構造に基づくとすれば、LLMのそれは、統計的パターン認識と確率的予測による表層的な「浅い理解」による処理に過ぎません。
それでもなお、この“浅い理解”が、規模の力によって非常に高い実用性を持つことは否定できません。
ゆえに私は、LLMの能力に驚嘆しつつも、「理解」という言葉の使い方には慎重であるべきだと考えています。とくに、人間と同等の“理解”を備えているかのような印象を与える文脈では、用語選択に注意すべきです。
参考文献(考える上で参考にしたもの)
- The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity arXiv:2506.06941
- The Illusion of the Illusion of Thinking arXiv:2506.09250
- DeepSeek-V3 Technical Report arXiv:2412.19437
- Mechanistic Indicators of Understanding in Large Language Mode arXiv:2507.08017